イベント情報
第40回自然科学研究機構シンポジウム 野村 英子
第40回自然科学研究機構シンポジウム 野村 英子

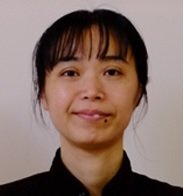
野村 英子(のむら ひでこ)
自然科学研究機構 国立天文台 教授
<略歴>
1996年 京都大学理学部 卒業
1996年 京都大学大学院理学研究科物理学・宇宙物理学専攻修士課程
1998年 京都大学大学院理学研究科物理学・宇宙物理学専攻博士後期課程
2001年 博士(理学)の学位取得(京都大学大学院理学研究科)
2001年 日本学術振興会特別研究員(PD) (京都大学大学院理学研究科物二教室)
2002年 Research Associate (Dept. of Physics, UMIST, UK)
2004年 COE研究員(PD) (神戸大学大学院自然科学研究科)
2006年 日本学術振興会海外特別研究員 (Queen's Univ. Belfast, UK)
2008年 京都大学大学院理学研究科宇宙物理学教室・助教
2013年 東京工業大学理学院地球惑星科学系・准教授
2019年 国立天文台科学研究部・教授
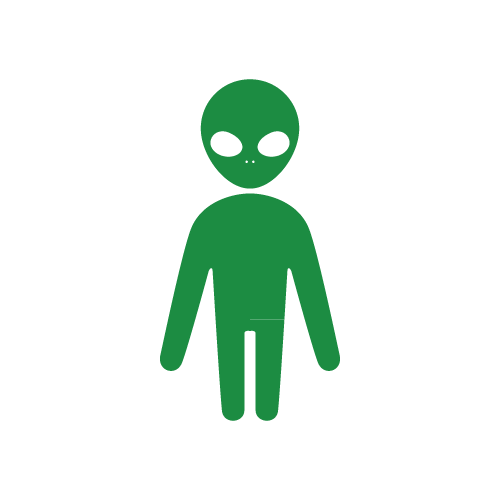
多様な惑星と生命が誕生する環境
我々の太陽系や、太陽系外の惑星系は、どのようにして誕生したのでしょうか?我々の生命の材料となるような物質は、太陽系外の惑星系にも存在しているのでしょうか?宇宙における物質の大部分は水素で、生命のもととなる炭素や窒素,酸素などの元素は、現在の太陽系付近の場合、そのわずか0.01%しか存在しません。この中で、地球のような岩石惑星に取り込まれる割合はさらにごくわずかで、元素によってその割合は異なります。現在の太陽系付近では、炭素や窒素,酸素の比率は同じくらいですが、地球においては、炭素は酸素の0.1%以下、窒素は0.01%以下しか存在しません。この違いはどのようにして生まれるのでしょうか?また、惑星系によって多様性があるのでしょうか?
太陽系も含めた惑星系は、原始惑星系円盤とよばれる、若い星のまわりの円盤状の天体の中で誕生します。すばる望遠鏡やアルマ望遠鏡などの最近の大型望遠鏡により、このような惑星が誕生する現場の観測が急速に進展しています。最近の観測によると、星や惑星が誕生する環境によって、また、その進化段階によって、物質の組成に違いがあることがわかってきました。本講演では、最新の観測によって明らかになりつつある、惑星が誕生する現場における物質の進化の研究を紹介し、様々な環境で多様な惑星、そして生命が誕生する可能性を考えます。
<先生の最近ハマっていることは何ですか?>
旅行、読書、最近は富士山の見える温泉地によく旅行します
