Press Room
イベント情報 詳細
第33回自然科学研究機構 川合 眞紀 機構長プレス懇談会
(機構長プレス懇談会は、報道各社の皆様と、ライターの皆様限定で開催しています。大変申し訳ありませんが、その他の皆様からのご参加希望につきましては、お断りをさせていただいております。何卒ご了承ください。)
開催概要
脳は、呼吸や代謝、恒常性の維持などの生命の根幹から、言語機能、認知・判断、感情、表現などの高次機能に至る、生物そのものの司令塔としての役割を果たしている器官です。とりわけ人は、他の動物よりもはるかに大脳皮質が大きく発達した、高機能な脳を持っています。人の脳機能は非常に複雑であり、その全容を解明するには至っていません。一概に人の脳を解明すると言っても、人を対象として観察できることには限界があります。そのため多くの研究者たちは、多種多様な動物を対象にさまざまな手法を用いて研究を行い、包括的に脳の仕組みを知ろうとしています。
今回は、自然科学研究機構の一機関であり、ヒトの機能の解明を目指す生理学研究所の最近の動向と将来について皆様にお話しさせていただくとともに、最新の脳神経科学研究のトピックスを取り上げます。近年、脳の認知機能研究の中で「予測符号化」という名称が話題にあがります。予測符号化とは、脳が過去に学習した経験を基に、外界の情報を予測しているという説です。例えば、静止画なのにあたかも動いているように視える錯視画像を見たことがある人は多いのではないでしょうか。この現象は、脳の中で行われた予測と、実際に目から入力される感覚情報との間に不一致(エラー)が起こるため引き起こされる現象です。つまり私たちの脳は、予測と外部から入力される情報との間のエラーを常に学習し、外界に対する予測をアップデートし続けることで、状況への判断や対応の精度を向上させているのです。これらの予測や学習についての脳内でのプロセスについては、近年の目覚ましい計測機器の発展から、次々と興味深い新発見がなされています。
講演に登壇する磯田昌岐教授らの研究のひとつに、他者の行動理解と自己の行為生成や認識との関係に着目したものがあります。特に、ある行為やそれに伴う結果について、それが自分に由来するものか、それとも他者やその他の要因に基づくものかを区別するという認知機構が、ヒト以外の霊長類でもみられることがわかりました。そして一方で、ヒトを特徴づける要素も浮き彫りになってきました。今回は、磯田教授らの研究成果を交えながら、他者の動きからそのこころを推測するという、その複雑な脳のメカニズムに迫っていきたいと思います。
ーーーーーーーーーー
日 時:令和7年3月24日(月)14時から2時間程度 (意見交換会を含む)
会 場:日本橋ライフサイエンスビルディング 2階201大会議室 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町2-3-11
オンライン配信:あり(ZOOM) オンライン視聴をご希望の方はメールにてお申し込みください。
ーーーーーーーーーー
講演者情報
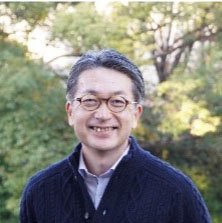
磯田 昌岐(いそだ まさき)
自然科学研究機構 生理学研究所 認知行動発達機構研究部門 教授
<略 歴>
新潟県中蒲原郡出身。新潟大学医学部医学科卒業。新潟大学脳研究所神経内科学教室に入局し、神経内科医として5年間臨床に従事。基礎研究の道を志し、医師を廃業して東北大学大学院医学系研究科に入学。2003年修了。米国NIH(ポスドク研究員)、理化学研究所脳科学総合研究センター(副チームリーダー)、沖縄科学技術研究基盤整備機構(代表研究者)、関西医科大学医学部(准教授)を経て、2016年より現職。好きな言葉は「人生に無駄なし」。

兼子 峰明(かねこ たかあき)
自然科学研究機構 生理学研究所 認知行動発達機構研究部門 特任助教
<略 歴>
愛知県蒲郡市出身。筑波大学生物学類卒。京都大学大学院理学研究科を2012年に修了、博士(理学)。京都大学文学研究科博士研究員、理化学研究所脳科学総合研究センター研究員、京都大学霊長類研究所特定助教を経て2023年4月より現職。
